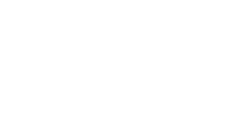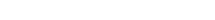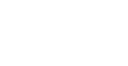お盆法要「歓喜会」のご案内・申し込み用紙の配布を始めました。
ご参詣ご希望でまだ案内が届いていない方は、お手数ですがご一報くださいませ。
合わせて慈法寺通信もお配りしています。
今号は「生死」について。
世間では「生死(せいし)」と読み、「生きる」と「死ぬ」を正反対で全く別のことと考えます。
ですが仏教では「生死(しょうじ)」と読み、お釈迦さまは「生死一如(しょうじいちにょ)」と言われました。
「生きる」と「死ぬ」はつながっていて一つであるという意味です。
続きは通信をご覧ください。ご門徒皆さまに、月参りやご法事でお届けします。
しばらくお休みしていた慈法寺通信を、新たな形で再開しました。
これまで肩に力を入れすぎ、正直に言うと皆さまに恰好をつけていましたが、今後は愚直にお伝えしていけたらと思います。
これを機に文字を大きくし、外部に発注していた構成も自分で挑戦してみました。
パソコンに詳しくないため読みにくい部分も多いですが、今号は納骨堂入り口に掲げられているお釈迦さまの言葉「俱会一処」について書いています。
ご門徒皆さまに、月参りやご法事でお届けたします。

お盆が近付くにつれて、月参りで伺うご門徒さんのお内仏近くに
盆提灯が飾られているお宅が次々と増えてきました。
50年以上前のアンティークなもの、ミニサイズでモダンなもの、
提灯に描かれている花模様も様々です。
盆提灯が届けられた時の思い出、送ってくださったご親族のお話し
盆提灯をきっかけに、いつもよりたくさんのお話しを聞くことができます。
楽しくてついつい次の約束に遅れがちになってしまいます。
季節のものを出したり片付けたりは大変だけど、
年々加速する酷暑のなか、和装で移動するのが辛いと感じる時もあるけど、
何年も何十年も経っても
亡き人をご縁に色褪せない思いを聞かせて頂けるお盆が、やっぱり好きです。





2024年6月29日、東別院 対面所に於いて
名古屋教区 第二十組 同朋大会が開催されました。
「君たちはどう生きているか」〜仏典童話を通して伝えたいこと〜
と題して、仏典童話作者であられる渡邊愛子先生にお話しいただきました。
数年をかけて企画された方の熱量を中心に、組内で何度も話し合い、
京都での渡邊先生との打ち合わせを経て、
なんと大会当日に仏典童話の朗読を、作者の渡邊先生の目の前で私が担当することに!
一方で二十組同朋会講師の祖父江志郎師にお願いして、スタッフ一同の事前学習会も開催しました。
日に日に緊張が高まる中、迎えた大会当日。
渡辺愛子先生の柔らかなバイタリティそのままのお話しに会場全体が引き込まれ
物語から気付かされる私の姿、登場人物一人一人の言動にも大きな意味があることを知り、
確かに仏典童話とはお釈迦さまの教えであるのだと、
記念に頂いた本を、いつの間にかギュッと抱きしめていました。
チケットを購入されたご門徒さんからは、
「他の仏典童話も読みたくて、帰宅してすぐにAmazonでポチりました!」
「こんな盛大な大会とは思わなかった」「童話のイメージが変わった。来てよかった!」
こんな嬉しい声が。
数年に一度の組の同朋大会。
教化委員として関わることができ、大変貴重な機会をいただきました。
おまけですが、慰労会では渡邊先生がわざわざご持参くださった本場のサリーを
女性スタッフたちに着せてくださり
緊張がほぐれて満面の笑みで写真に収まる私でした。


先日、ご縁ある方々と弾丸日帰りツアーで富山県〜石川県へ。
一番の目的は城端別院善徳寺の虫干法会です。
所有する宝物が虫干しを兼ねて一般公開される、年に一度の貴重な機会に初めて訪れることができました。
加賀藩前田家から贈られた宝物が多く、それはそれは雅な宝物の数々に見とれて。
各部屋に解説して下さる方がおられて、更に座り込んで見学してしまいました。



本堂でご法話を聴聞し、手作りのお斎には名物の鯖ずしが!
山門に上がることもできました。

その後は同行した方のお知り合いのお寺へ伺ったり、暁烏敏師のお寺へ伺って広〜い境内を案内して頂いたり。
富山と石川の名物も各場所でしっかり食し、大充実の弾丸日帰りツアーとなりました。
日頃は行動範囲がかなり狭い私、ご縁をいただき感激でした。
慈法寺通信 2023年6月号ができました。今号は蓮如上人のお言葉「必ず五人は五人ながら意巧にきく物なり。よくよく談合すべき。」から、私がお聞きしているところを中心に掲載しています。
また、団体参拝で訪れた慶讃法要のご報告、帰敬式再考委員会の一員として新たなリーフレット作成に関わらせて頂いた「生前法名」について などなどです。
ご門徒皆さまに、月参りやご法事の際にお届けいたします。
そして今月18日㈰に、名古屋別院定例法話にてお話しさせて頂くことになりました。背伸びをせずに、ご法事などで日頃からご門徒皆さまにお伝えしていることをお話ししてこようと思っています。
名古屋別院では毎日法話が行われています。どなたでもご自由にご聴聞いただけます。
多くの先達によって時代を超えて私たちまで伝えられてきた、お釈迦さまや親鸞聖人の教え・願いに耳を傾けてみませんか。
午前9:30〜9:50 於:本堂
午前11:10〜11:40 於:対面所
午後1:00〜1:30 於:対面所


本年は「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年」に当たり、3月25日から4月29日まで京都のご本山にて記念のご法要が厳修されました。全国から僧侶・ご門徒が集まり、境内を中心に稚児行列や舞楽・ワークショップ・特別展示など様々な催しが開かれ、大変な賑わいでした。
今回は史上初めて阿弥陀堂と御影堂で同時に勤行、両堂一体となっての正信偈が響きわたり、いっそう荘厳な雰囲気でした。お念仏の歴史はこうして、50年前にも100年前にも無数の方々が同じ場で南無阿弥陀仏と唱え、慶(よろこ)びを共にして紡いでこられたのでしょう。
YouTubeでは解説付きでライブ映像が配信されています。ぜひ、「東本願寺慶讃法要」で検索してみてください。
宗教法人 慈法寺
〒453-0047愛知県名古屋市中村区元中村町2-38